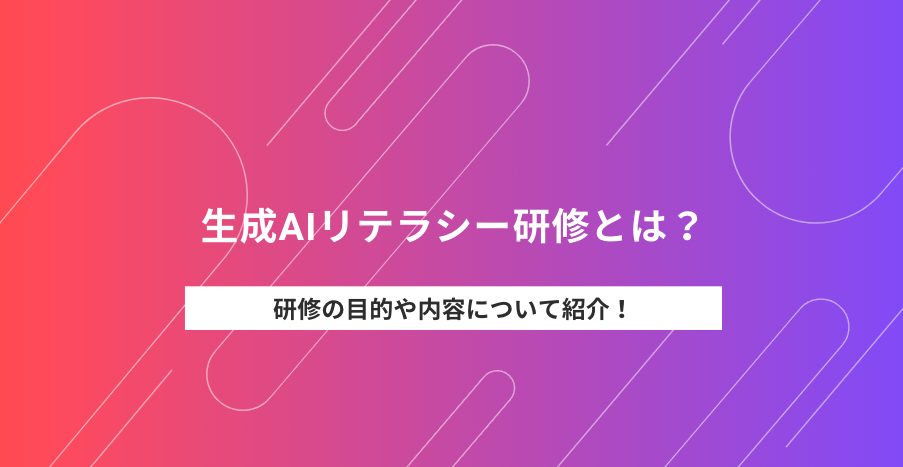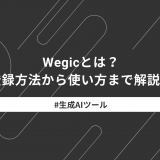生成AIとは、深層学習・機械学習を活用して自動でコンテンツを生成するAIのことです。生成できるものは文章・画像・動画・音楽など多岐にわたり、便利な機能として活用されるようになりました。ただし、生成AIの使用にはリスクもあり、正しい知識がないと却ってデメリットの方が大きくなるため注意が必要です。
本記事では、生成AIリテラシー研修の目的・内容について解説します。リスクマネジメントの一環として導入している企業も多いため、参考にしてみましょう。
最短ルートで
生成AIを使いこなしたい方へ
- 生成AIを使ってみたが、思うような
結果が出ない - 生成AIの活用方法がわからない
- AIを使って業務を効率化したい
生成AIコース無料体験してみませんか?
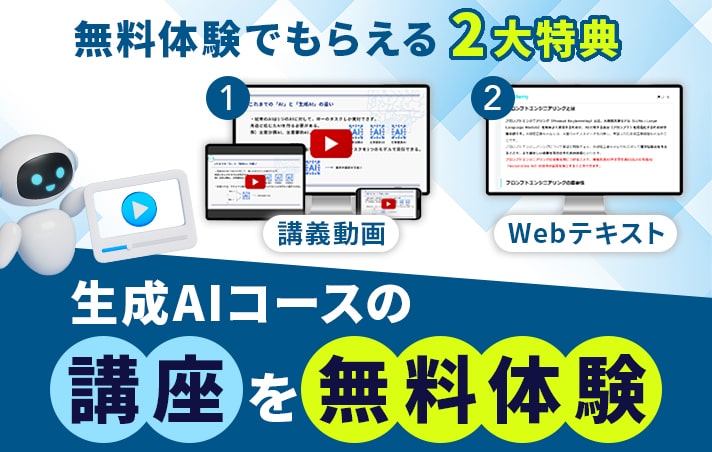
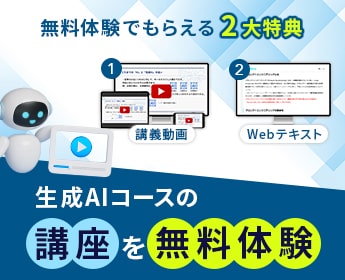
- 無料で120以上の教材を学び放題!
- 理解度を記録して進捗管理できる!
- テキストの重要箇所にハイライトを
残せる!
1分で簡単!無料!
無料体験して特典を受け取る初心者でも生成AIを活用できるようになりたい企業様へ
「生成AIで何ができて、何ができないの?」そんな疑問をお持ちの方から、さらに効率的に使いたい方まで。本講座は、単に生成AIの概要が学べるだけではありません。AIの本質を理解し、自分の力で業務の改善や問題解決に取り組めるようになります。AI Academyの生成AIコースの受講をご検討ください。
生成AIがもつリスク
生成AIリテラシー研修が特に注目されている理由として、生成AIがもつ利便性の裏側に、多くのリスクがあることが挙げられます。便利で使い勝手の良いツールだからといって自由に活用した場合、リスクやデメリットの方が大きくなって会社の基盤を揺るがす大きな問題に発展してしまいます。
以下では、生成AIがもつリスクについて解説します。なぜ生成AIリテラシーの強化が必要なのか、探っていきましょう。
情報漏洩リスク
生成AIを利用したことで、自社がもつ個人情報・機密情報が漏洩することがあります。例えば顧客サポートに自然言語処理能力をもつ生成AIを利用し、チャットボットのように活用した場合、入力された個人情報が他社への回答に使われてしまう可能性があるため注意しましょう。個人情報を意図しない形で使われてしまったり、悪意のある他者から個人情報を抜き取られてしまったりする可能性があるため、会社としての信頼度を大きく損ねる要因となります。
また、機密情報が流出した場合、社外秘で進めているプロジェクトの詳細や新たな企画・開発に関する要件定義が明るみになり、ビジネスチャンスの損失になることも。運用を徹底し、どんな情報をどう生成AIで活用していくかシミュレーションする必要があります。
権利侵害リスク
インターネット上の情報を自由に組み合わせながらコンテンツ制作する生成AIの場合、権利侵害のリスクが高まります。例えば他社のデザイナーが考案した既存のデザインを使って類似の案としてしまったり、書籍・動画作品(映画やYouTubeチャンネルなど)・キャッチコピーが似通ってしまったりする可能性があるため注意しましょう。類似性・依拠性・創作性を満たしてしまい、著作権侵害や知的財産権侵害で訴えられる恐れがあります。
「デザインを丸パクりする会社である」「類似性があると気づけもしない会社なのか」と業界内での評判が悪くなり、大きな信用喪失に繋がるかもしれません。手軽に利用できる生成AIにどんなリスクがあるのか知り、正しく監督する必要があります。
ハルシネーションリスク
ハルシネーションは「幻覚」という意味をもつ言葉であり、生成AIが事実に基づかないコンテンツを生成してしまうことを指します。生成AIは情報の断片をつなぎあわせて「もっともらしいコンテンツ」を作り出してしまうことがあり、コンテンツをそのまま公開してしまうことは危険です。
当然ファクトチェックをしながら公開していくことになりますが、ファクトチェックにもデメリットがあります。そもそもファクトチェックの意義を知らなかったり、ファクトチェックにばかり時間がかかったりする場合、生成AI活用のメリットが得られません。ハルシネーションリスクを正しく防ぐ方法を学び、確実性の高いコンテンツ制作としていく必要が出てきます。
生成AIリテラシー研修の目的・内容
生成AIリテラシー研修では、主に以下について学びます。専門的な知識やスキルを習得するほか、実際に自社でAIを活用する方法や扱う際の注意点についても学べるため、活用していきましょう。
生成AIの基本的な使い方・操作
生成AIとは何か、基本的な項目を学びながら使い方・操作を習得します。深層学習・機械学習・ディープラーニング・自然言語処理(NLP)など主なAI技術について学ぶことも多く、技術に関する知識習得を含むこともあります。
また、実際の事例を見ながら生成AIの代表的な活用法を学ぶことも多いです。「生成AIという単語は知っているが、具体的にどう業務に役立てられるかイメージできない」という人は少なくありません。自社での活用法を探るヒントを得るきっかけにもなるため、リテラシー以外の部分から網羅的に学ぶ研修プログラムにしていきましょう。
AIガバナンスと利用ポリシー
ガバナンスとは「統制」「統治」を意味する言葉であり、近年は企業組織の目標達成や長期的な発展に向けて欠かせないものであるという考え方が広がっています。AIガバナンスでは、生成AIが孕んでいるリスクやデメリットを学び、リスクマネジメントについて考えます。特にAI技術を開発・利用・提供する際の社会規範や法令など、適切に統制するための運用手法を学ぶことができるため、AIを取り巻く社会基盤についてチェックしたい時に活用しましょう。
また、自社で生成AIを利用する前段階にはポリシーを策定し、「問題なく生成AIのメリットを享受できるか」「ポリシーの内容に抜け穴や見落としがないか」をチェックします。実際の企業事例を見ながら必須項目を探っていく研修にすることが多く、AIの適正活用を推進する組織としての基礎を作り上げます。
AI活用の制限に関するディスカッション
AI活用の制限に関するディスカッションでは、「どこまでAIを使っていいか(どこから使ってはいけないか)」およびその理由について議論します。倫理的な課題を含むことが多いため正解のない問いになりやすく、そのためディスカッション方式になることが多いです。そのほか、プレゼンテーション形式による意見交換やワークショップなどの形式で実施されることもあります。
また、世界的な規制のトレンドについても学びます。欧州連合(EU)では生成AI利用に関する包括的な規制案を作成しており、特に顔認証やオンライン広告への応用などリスクの高いコンテンツ生成に関する制限を設ける動きが出ているため注目しておきましょう。世界のトレンドも学びながらディスカッションすれば、より有意義な研修となります。
実務で役立つAIツールの活用
実際にAIツールを使う時間を設け、模擬プロジェクトやデータサンプルを使った分析にチャレンジします。実践的なセッションであるため学びが実務に直結しやすく、生成AIに対する苦手意識を強める研修として終わらないようにする工夫も含まれています。
「自社にAIを導入した場合の活用法」「今の業務で役立ちそうな使い方」など、参加者目線でのプログラムにしていくのがポイント。ルールを守って生成AIを使えるようになれば苦手意識も払拭しやすく、研修終了後の生産性向上に貢献します。
生成AIリテラシー研修に対応しているおすすめの法人5選
ここでは、生成AIリテラシー研修に対応している研修会社を紹介します。「生成AIとは何か」という基本的な項目から、実際のリスクやデメリットも見据えた活用法まで習得できるため、スキルアップに役立てましょう。
以下では、研修会社ごとの特徴について解説します。
AI Academy Business
AI Academy Businessは短期間で実務レベルのAI活用スキルを習得するための研修プログラムを多数提供しており、生成AIリテラシー研修やプロンプトエンジニアリングに関するカリキュラムも整備されています。AIツールの活用法や活用事例の紹介など専門的なことも学べるうえ、実務を想定した演習ができるため、組織全体のAIレベル向上に貢献します。
また、Pythonを使ったAIプログラミングやデータサイエンスなど、専門職向けの研修も可能です。エンジニアやプログラマーなど生成AIツールの開発を担う専門職向けの内容と、生成AIを使う現場向けの内容とでアレンジすることもできるため相談してみましょう。
アガルート
アガルートでは「AI・DX・データ分析・活用研修」を実施しており、人工知能・機械学習・ディープラーニングなどの重要概念を正しく理解できます。生成AIリテラシー研修では生成AIの基本から活用方法まで体系的に習得できる研修プログラムを用意しており、自社業務の活用アイデアを考えられるのがポイント。実際に活用することを想定したリスクマネジメントや注意点も細かく教えてもらえるため、現場目線での「OKなこと」「NGなこと」がイメージできます。
また、IT全般に関するリテラシー研修も開催しているため、新入社員や新たにマネージャー・管理者になった人を参加させるのにおすすめ。ITやAIに関する幅広い知識を身につけながらリスク対策としていきましょう。
インターネット・アカデミー
インターネット・アカデミーでは、1名から多人数までさまざまな規模に応じて研修プログラムを考案してくれるのが特徴です。研修内容は自由にカスタマイズできるほか、助成金を使って研修費用を抑えてくれる手法も教えてくれるため、コストパフォーマンスが良いのがメリット。生成AIを活用した業務効率化(DX)やAIに関する資格取得など、「AIを学ぶ」ことに+αした研修にすることも可能です。
「AIリテラシー研修」では、他社事例を踏まえて自社へのAIサービスの導入判断ができるレベルを目指します。特に管理職が知っておくべきIT・AIのリテラシーが身につく内容になっているため、技術的な知識や専門用語も学びながら習得しておきましょう。そのほか、クラウド・ビッグデータ・5Gなど、AIについて理解するうえでの前提となる技術や用途について学習することも可能です。
picture academy(ピクアカ)
picture academy(通称:ピクアカ)は、IoT・AI・データサイエンス・G検定・イノベーションについて学べるコンテンツを提供しています。データサイエンスのプロフェッショナルGRIのデータ分析官がカリキュラム制作を担当しており、専門的な内容をオンラインで手軽に学べるのがポイント。法人利用はもちろん、個人利用もできるため個人的なスキルアップの場として活用してもよいでしょう。
「生成AIリテラシー研修」では、主にChatGPTの活用法について学びます。カリキュラム内には法律・倫理の項目が含まれており、個人情報および著作権の保護やセキュリティ対策についても習得できるため、活用していきましょう。文章生成AIを使いこなす演習や拡張機能の使い方も学べるなど、実務に即した内容となっています。
インソース
インソースは基本的なビジネスマナーから生成AIの活用まで、幅広い研修ジャンルを取り扱っているのが特徴です。もともと社会人教育・コンサルティングに強みのある会社なため、「どんな研修にすべきかわからない」などぼんやりとした悩みにも対応してくれるのがメリット。結果、生成AIリテラシー研修にすることはもちろん、ほかの研修プログラムと組み合わせながら自社の課題を解消できます。
なお、AI研修では管理者向けのプログラムと現場で働く従業員向けのプログラムとを分けられるため相談してみましょう。導入事例やリスクを知ることも、実際の活用法を知ることもできるため、業務効率化とリスクマネジメントの視点を同時に広げることも可能です。社内のルールを明確化しつつ、積極的な生成AI活用を推進したい企業におすすめです。
まとめ
生成AIは非常に便利なツールであり、既に業種・企業規模問わず幅広く導入されています。一方、リスクを知らないまま使うと情報漏洩・著作権侵害・ハルシネーションを生むなど大きなトラブルになりやすく、場合によっては大きな社会問題となるため注意しましょう。自社の信用を損ねることなく、本来意図していた業務効率化・生産性向上のために生成AIを使うには、事前にリテラシーの視点を持っておくことが大切です。
自社で生成AIリテラシー研修のプログラムを考案するのが難しい時は、外部の専門会社を頼りましょう。AI Academy Businessでも生成AIのリスクや適切な使い方、ポリシー策定のポイントなどを細かく指導しているためお気軽にご相談ください。