最短ルートで
生成AIを使いこなしたい方へ
- 生成AIを使ってみたが、思うような
結果が出ない - 生成AIの活用方法がわからない
- AIを使って業務を効率化したい
生成AIコース無料体験してみませんか?
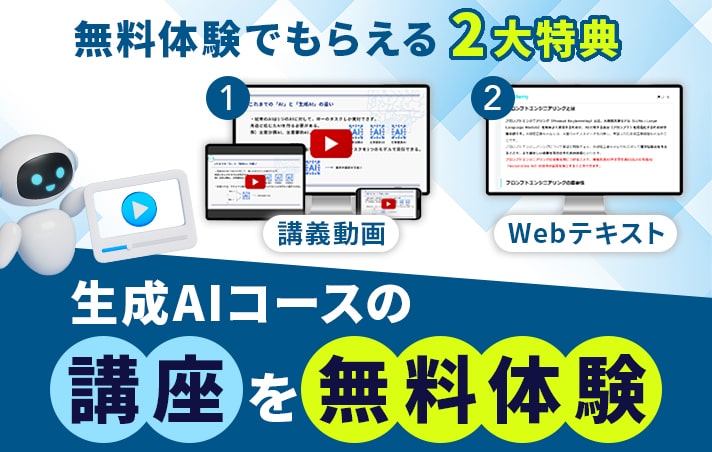
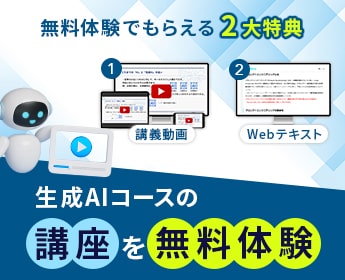
- 無料で120以上の教材を学び放題!
- 理解度を記録して進捗管理できる!
- テキストの重要箇所にハイライトを
残せる!
1分で簡単!無料!
無料体験して特典を受け取る生産性を高めるために、生成AIツールを導入する企業や個人が増えています。しかし「AIツールが多すぎて違いがわからない」「用途に合ったものを選ぶのが難しい」と悩んでいる方も多いでしょう。
そこで、この記事ではおすすめの生成AIツール15選を紹介します。文章作成・画像制作・動画編集など、各分野の人気ツールを紹介するので、自分に合った生成AIツールを見つけたい方は最後までご覧ください。
文章作成におすすめの生成AIツール3選
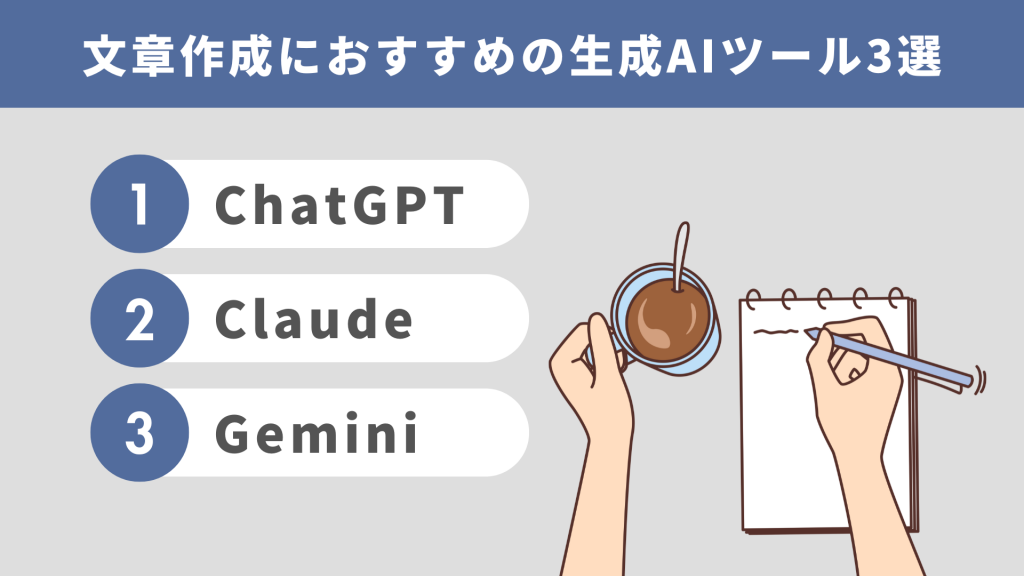
文章作成を効率化したい方は、次のツールをチェックしてみてください。
- ChatGPT
- Claude
- Gemini
ChatGPT
ChatGPTは、OpenAIが開発した生成AIです。与えられたテーマから自然で読みやすい文章を作れるため、記事の下書きや企画書作り、メール文面の作成といったさまざまな業務に活用されています。
「やさしい言葉で説明して」「専門的な内容をまとめて」など、指示を少し変えるだけで文体や語彙も自動で調整してくれます。文章量の調整や言い換えも簡単に行えるので、悩んでいる方はまずChatGPTから試してみましょう。
Claude
Claudeは、Anthropic社が開発した生成AIです。長文の読解や要約などを得意とし、複雑な文脈でも意図を正確にくみ取り、わかりやすい文章にまとめます。
日本語の出力にも優れていて、読者に配慮した柔らかい表現を自然に使いこなします。やや抽象的な指示にも柔軟に対応できるため、原稿のトーンを整えたり、読者層に合わせて表現を変えたりするときにも最適です。
企業の担当者はもちろん、ライターや編集者といった日常的に文章を執筆・構成する方々にも広く愛用されています。
Gemini
Geminiは、Googleが提供する生成AIです。Google検索と連携して最新情報をもとに文章を作成できるため、リサーチを伴う記事やレポートの作成に適しています。
さらに、Googleの各サービスとも連携して活用することも可能です。たとえば、Googleドキュメントでは「この段落をやさしく要約して」「企画書の導入文を300字で書いて」と指示すると、AIが自動的に文章を生成・編集します。
スプレッドシートでは、表のひな型作成や列名の提案をAIが行い、作業を効率化します。Googleアカウントを持っていれば簡単に使えるので、初めてAIを試す方にも最適です。
画像制作におすすめの生成AIツール3選
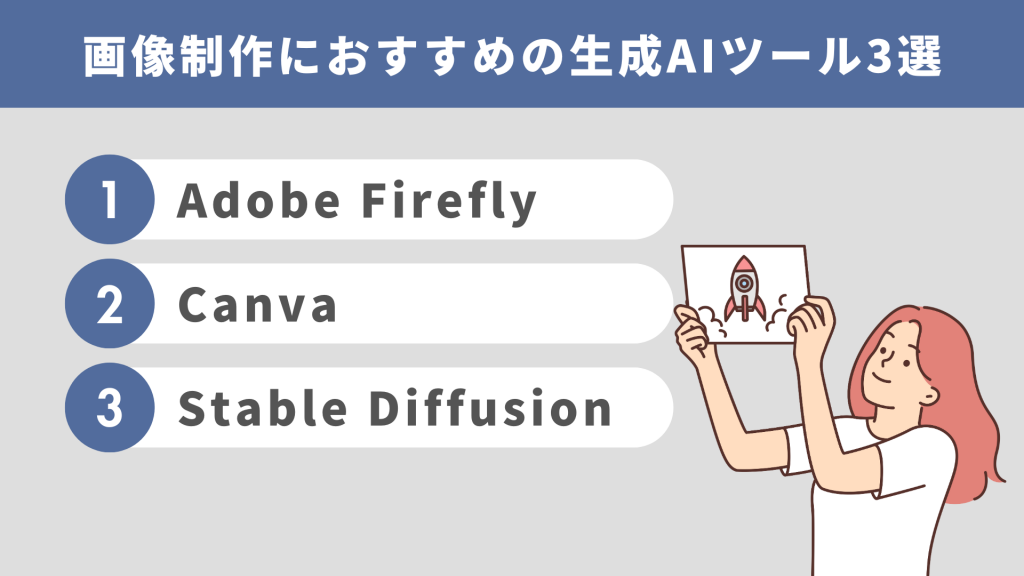
高品質な画像を短時間で作成したい場合は、次のツールを活用してみましょう。
- Adobe Firefly
- Canva
- Stable Diffusion
Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、Adobeが開発した画像生成に特化した生成AIです。テキストを入力するだけで高品質な画像を作成できるほか、既存の画像を自然に修正したり、背景を入れ替えたりすることも可能です。
さらに、PhotoshopやIllustratorなどのAdobe製品と連携できるため、これまでの制作フローにそのまま組み込めます。たとえば、製品カタログのレイアウトを調整しながら、その場でFireflyを使って画像を差し替えられるので、素材探しや加工にかかる時間を大幅に短縮できます。
商用利用にも対応しており、安心して業務やプロジェクトに取り入れられる点も魅力です。
Canva
Canvaは、Canva社が開発した生成AI搭載のデザインツールです。「マジック生成」という独自の機能を使うと、テキストを入力するだけで目的に合った画像を生成できます。
テンプレートの種類も豊富で、名刺やプレゼン資料、広告バナーといった幅広い用途に対応しています。生成した画像を組み合わせながらその場で編集できるため、デザイン経験がない方でも短時間で高品質なデザインに仕上げられるでしょう。
また、OpenAIが提供している画像生成AI「DALL・E」もCanvaに統合されており、用途や好みに合わせて使い分けられるのも特徴です。
Stable Diffusion
Stable Diffusionは、Stability AIが開発した画像生成AIです。テキストで指示を入力するだけで、アニメ風のイラストや写真のようなリアルな画像、CG風のグラフィックまで自在に作成できます。
また、一般的なツールとは異なり、オープンソース(誰でも無料で利用・改良できる仕組み)として公開されているのが特徴です。パソコンにインストールしてローカル環境で動作させられるため、データを社内で安全に管理したい企業にも適しています。
日本語に完全に対応しておらず、操作にはある程度の知識が求められますが、理想の表現を追求したい方におすすめのツールです。
その他、Midjourneyもおすすめです。
動画制作におすすめの生成AIツール3選
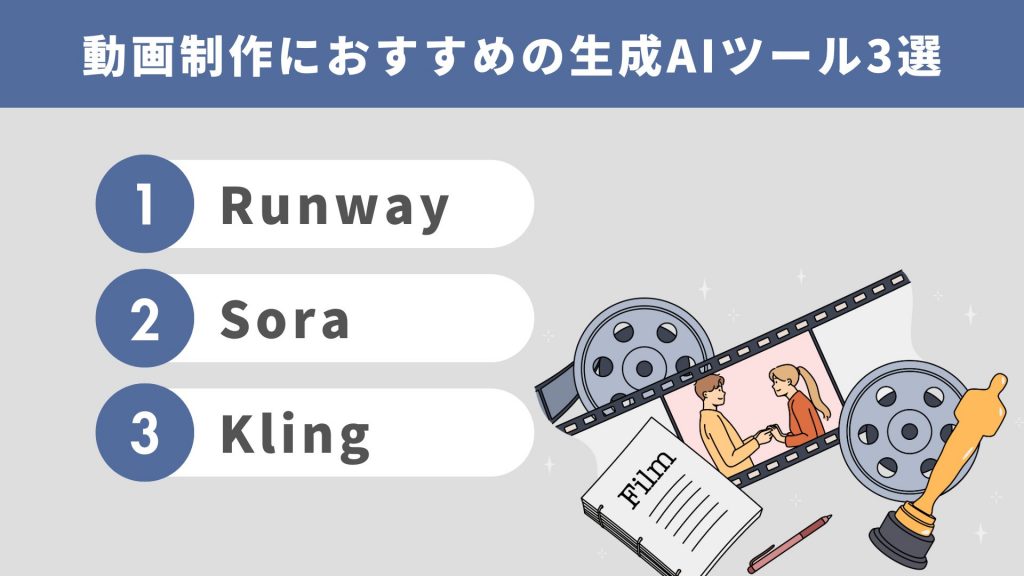
動画制作におすすめの生成AIツールは、以下の3つです。
- Runway
- Sora
- Kling
Runway
Runwayは、Runway AI社が開発した動画制作向けの生成AIです。テキストを入力するだけで映像を生成したり、既存の動画を編集したりできるため、専門的な知識がなくても高品質な映像を作成できます。
背景の自動削除や被写体の置き換え、カメラワークの追加などをAIが自動で行うので、これまで時間のかかっていた工程を大幅に短縮できるのも魅力です。また、Adobe Premiere ProやAfter Effectsといった他の制作ツールとも、スムーズに連携できる設計になっています。
そのため、既存の編集フローを維持したまま作業効率を高めたい方にもおすすめです。
Sora
Soraは、OpenAIが提供する動画生成AIです。ユーザーの指示をもとに、指定した内容・雰囲気・スタイルの短尺動画を自動生成できます。
テキストだけでなく、すでにある動画を取り込んで延長したり、一部分を作り替えるといった編集機能も用意されています。そのため、映像制作のアイデア出しやコンセプト検証を効率よく進めたいクリエイターにとっても有用です。
縦型・正方形・横型など、複数のアスペクト比に対応した短尺動画をすばやく量産できるので、SNSや広告向けのコンテンツ制作にも適しています。
Kling
Klingは、中国の快手(Kuaishou)社が開発した動画生成AIです。テキストだけでなく、静止画から最大フルHD(1080p)の短尺動画を生成できます。
そのため、見た目や構図を指定して、思い描いた映像表現をより正確に再現できます。AI動画はキャラクターや商品といった被写体の見た目が途中で変わってしまうという問題が発生しやすいです。
しかし、Klingには複数の参照画像から外見の一貫性を保つ機能が備わっており、アニメやプロモーション動画の分野でも活用が期待されています。
その他、Veo 3.1もおすすめです。
情報収集におすすめの生成AIツール3選
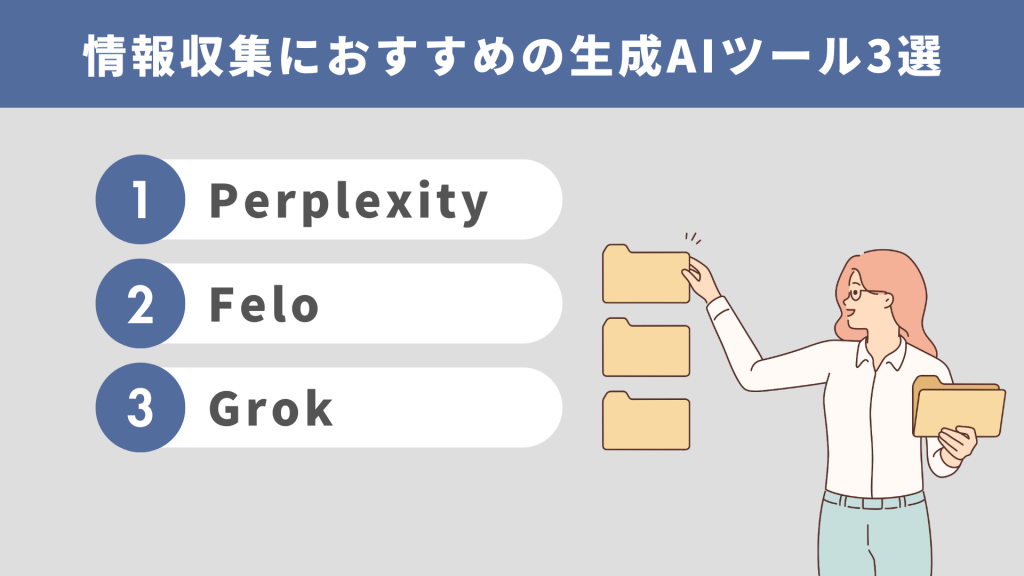
日々の情報収集に時間がかかっている方は、次の3つのツールを活用してみてください。
- Perplexity
- Felo
- Grok
Perplexity
Perplexityは、Perplexity AI社が開発した情報検索型の生成AIです。「質問に対して根拠を示しながら答える」のが特徴で、複数の情報源をもとに内容を整理し、要約とともに回答を提示します。
参照リンクが明示されるので、信頼性を自分で確かめながら競合分析や市場調査に活用することが可能です。たとえば「IT業界の最新動向」や「国内で注目されているスタートアップ」のような抽象的なテーマでも、短時間で具体的な情報を得られます。
情報収集から資料作成、ファクトチェックまでを一連の流れで完結できるため、法人でも安心して導入できるでしょう。
Felo
Feloは、Felo株式会社が開発している生成AI検索ツールです。質問を入力すると、Web上の複数ソースを横断して要点を整理し、根拠(参照リンク)付きで回答を提示します。
日本発のツールのため、国内の情報を集めるのが得意で、生成される文章も自然で読みやすいです。検索だけでなく、ファイルやリンクをそのまま取り込んで、スライドやWebページに仕上げることも可能です。
さらに「Felo Subtitles」という拡張機能を使うと、ZoomやYouTubeの音声をその場で文字起こし・翻訳して字幕表示できます。この一連の機能によって、リサーチから資料化、社内外への共有までを短時間で回せるようになるでしょう。
Grok
Grokは、イーロン・マスク氏が立ち上げた企業「xAI」が開発した生成AIです。X(旧Twitter)上で利用でき、SNS上の最新情報をもとに回答を生成できるのが特徴です。
たとえば、新製品の評判や業界の話題を調べる際、関連する投稿内容をまとめて分析し、全体像をわかりやすく提示します。さらに、コード生成や画像生成にも対応しており、幅広い用途に活用できます。
その他、ChatGPTやGeminiのDeep Research や Manusのワイドリサーチもおすすめです。
業務効率化におすすめの生成AIツール3選
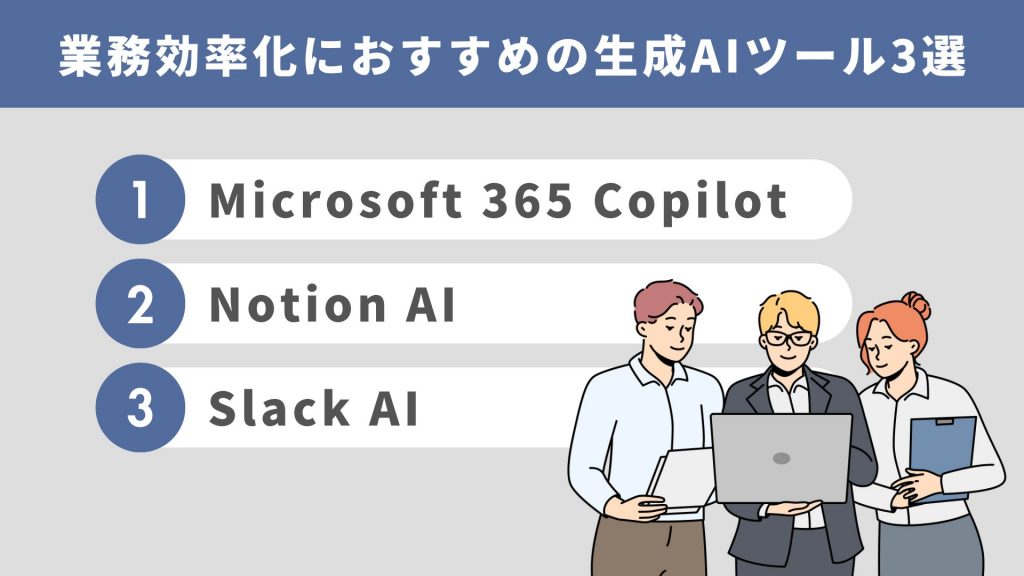
仕事の生産性を高めたい方は、以下の生成AIツールをチェックしてみましょう。
- Microsoft 365 Copilot
- Notion AI
- Slack AI
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilotは、Microsoftが提供する業務支援型の生成AIです。Word・Excel・PowerPointなどのOfficeアプリに組み込まれており、日常業務の中で直接AIを活用できるのが特徴です。
たとえば、Wordでは文書の下書き作成や要約、Excelではデータの整理や分析を自動で行えます。既存の社内データを活かしながら自然な言葉で指示できるため、文書作成や分析にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
さらに、OutlookやTeamsとの連携により、会議内容の整理やメール要約といったタスクを効率化できます。
Notion AI
Notion AIは、Notion Labs社が提供する生成AIです。ノート・ドキュメント管理ツール「Notion」に統合されており、議事録の自動要約や企画書のドラフト作成などを通じて、日常業務を効率化できます。
Notionを社内の情報共有基盤として利用している企業であれば、AI機能を組み合わせることでチーム全体の生産性を大幅に高められるでしょう。さらに、プロジェクト管理でNotionを活用している場合は、AIがタスクの整理や進捗レポートの作成を自動化し、その結果をメンバー間で即共有できます。
多言語対応のため、海外拠点を含むグローバルなチーム運営にも最適です。
Slack AI
Slack AIは、Salesforce社が提供する生成AIです。ビジネスチャット「Slack」に統合されており、ワークスペース内のメッセージやファイルをもとに文章作成や要約を行えます。
「昨日の会議で決まったことは?」「このスレッドの結論・担当者・締切を箇条書きで教えて」と入力すると、要点を整理してわかりやすく提示します。これにより、情報の見落としを防ぎ、チーム全体の意思疎通がスムーズになるでしょう。
参照範囲はユーザーの権限内に限定されているため、セキュリティやプライバシー保護の面でも安心です。
その他、業務自動化ツールとして、Google Workspace Flows やDify、n8nなどもおすすめです。
生成AIに関するよくある質問
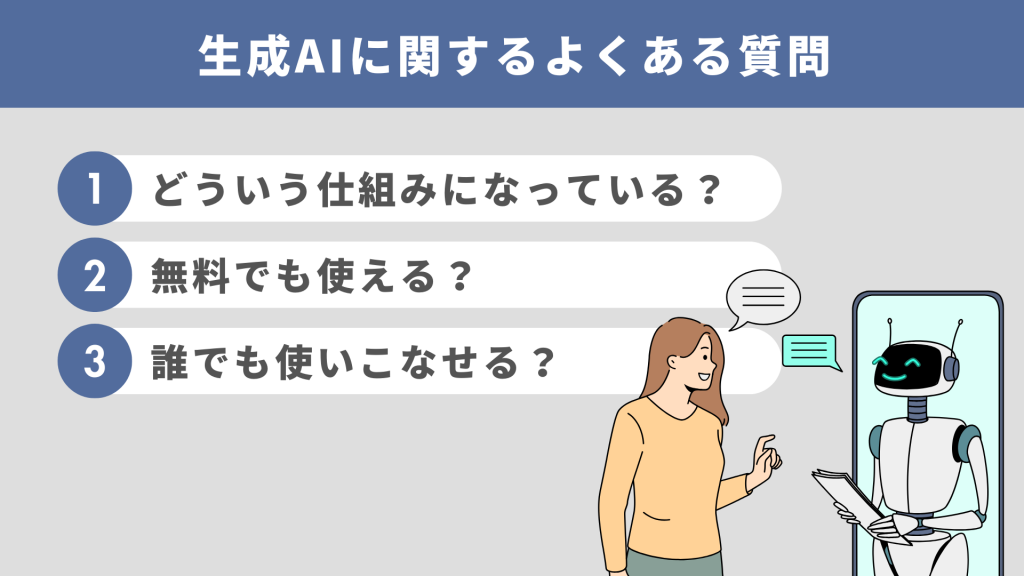
生成AIを活用する前に、よくある質問も確認しておきましょう。
- どういう仕組みになっている?
- 無料でも使える?
- 誰でも使いこなせる?
どういう仕組みになっている?
生成AIは、人間が書いた文章や作成した画像を解析してパターンを理解することで、新しい内容を自動的に生み出します。文章生成では、質問や指示の意図を読み取り、過去に学習した表現をもとに自然で流れのある応答を作成します。
一方、画像生成は入力されたテキストをもとにイメージを構築し、構図・色・質感などを最適化する仕組みです。このように、膨大なデータをもとに統計的な予測を重ねることで、人間が作ったような自然なアウトプットを生成します。
詳しい仕組みについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:生成AI(ジェネレーティブAI)とは?仕組みやできることを簡単に解説
無料でも使える?
現在、多くの生成AIツールが無料プランを提供しており、ユーザーはアカウント登録のみで基本機能を試せます。たとえば、ChatGPTやClaudeなどの主要ツールでは、文章生成や質問応答といった機能をすぐに体験可能です。
無料プランでは利用回数や機能に一部制限がありますが、使い勝手や精度を確認するには十分です。無料で使える生成AIツールを探している方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:【目的別】無料で使える生成AIツール12選!注意点や学習方法も解説!
誰でも使いこなせる?
ほとんどの生成AIは専門知識がなくても使えるよう設計されており、直感的な操作で利用できます。日本語で指示を与えるだけで結果が得られるため、特別なプログラミングスキルは不要です。
しかし、生成AIで望みどおりの成果を得るには、入力する指示文(プロンプト)の工夫が欠かせません。そのため、業務効率化を本格的に進めたい場合は、生成AIの使い方を体系的に学べるスクールを活用するのがおすすめです。
たとえば、アガルートの「生成AIコース」では、生成AIの基礎からChatGPTの操作、実務での応用方法までを段階的に学べるカリキュラムが整っています。レポートの自動作成や競合調査の効率化など、業務に直結した演習も充実しており、実践力を短期間で高められます。
現役エンジニアによる個別サポートも受けられるので、確実にスキルを伸ばしたい方は積極的に活用してみてください。
まとめ
この記事では、用途別におすすめの生成AIツールを解説しました。生成AIを上手に使うことで、コンテンツ制作から情報収集まで幅広い作業を効率化できます。
また、業務効率化に特化したツールを使えば、情報共有やタスク管理もスムーズになります。無料で試せるサービスも多いので、生成AIに興味がある方はこの記事を参考にしながら、目的に合ったものを使ってみてください。
生成AIを実務で使いこなしたい方は、AIに特化したスクールを活用してみましょう。たとえば、アガルートの「生成AIコース」では、まず生成AIの概要やChatGPTの基本操作など、基礎から丁寧に学べます。
その後、アプリ開発やデータ分析の実践演習に取り組むため、初心者でも安心してステップアップできます。現役エンジニアによる個別サポート付きのプランもあるので、即戦力となるスキルを身につけたい方はぜひチェックしてみてください。





